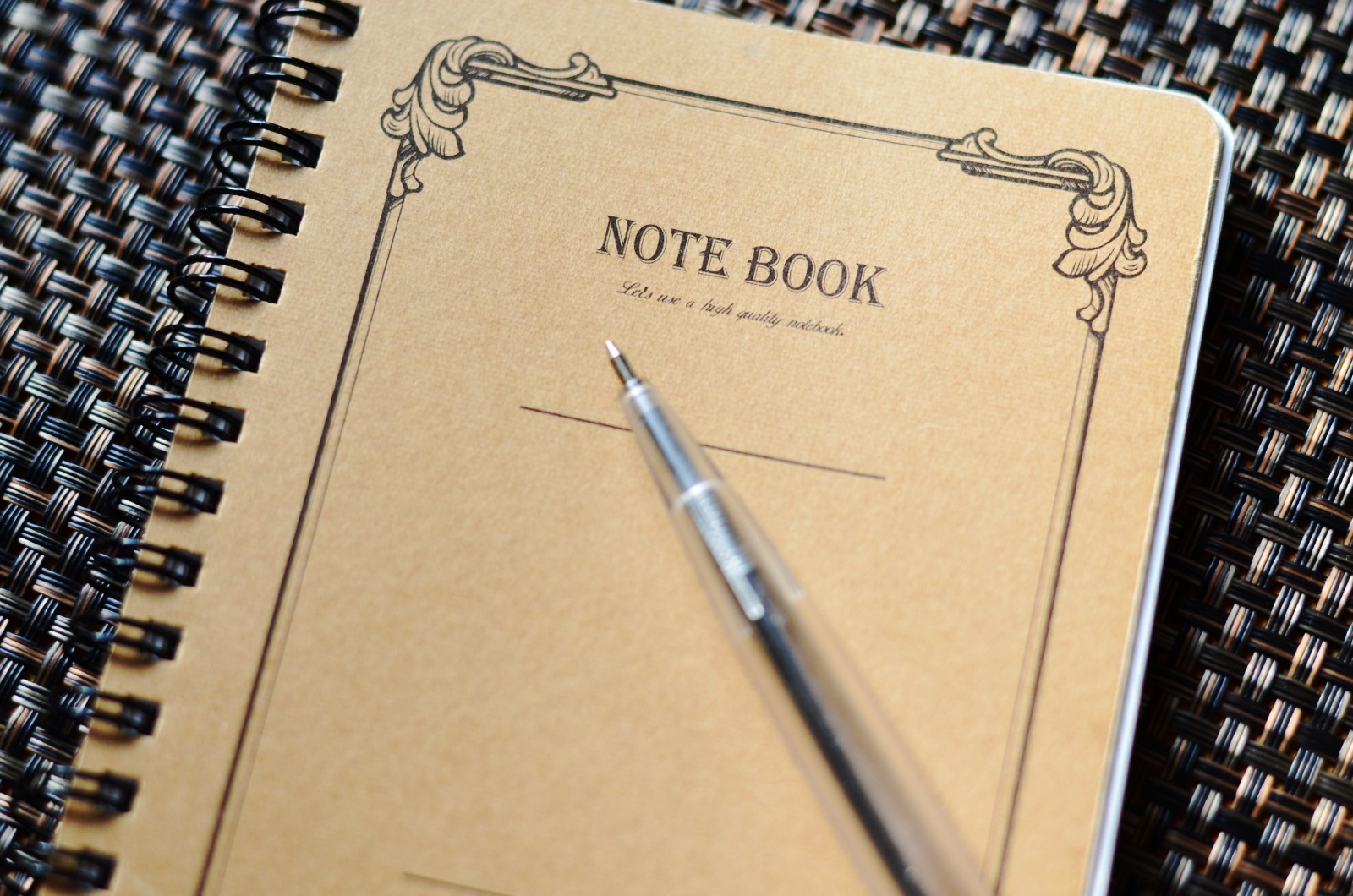先月、人生初の胃カメラを経験しましたが、個人的には二度と経験したくないほど辛かったです。
喉の部分に、水飴状の部分麻酔をしたにも関わらずです。
でも一度、どういう辛さかを理解すると、今後もし2度目を実施しないといけないとき、辛さは軽減されるのかもしれません。わかりませんが。。
今日は、世界で初めて全身麻酔の手術を行った日本人医師の物語を取り上げます。
全身麻酔「世界初成功は江戸時代の日本人」の凄さ
手術に使われる麻酔薬の開発に力を注いだ日本人について解説します(写真:マハロ/PIXTA) 手術に使われる麻酔薬の開発に力を注いだ日本人について解説します(写真:マハロ/PIXTA)
今や医療手術に欠かせない「麻酔薬」。それを開発し、世界で初めて全身麻酔の手術を行ったのが実は日本人医師であることをご存じだろうか。男の名前は華岡青洲。麻酔薬が開発される前の手術とは、耐えがたい痛みを伴う悲惨なものだった。命をかけて麻酔薬の開発にあたった青洲とその妻の物語を、東洋経済オンラインで「近代日本を創造したリアリスト 大久保利通の正体」を連載する真山知幸氏が解説する。
※本稿は真山氏の新著『泣ける日本史 教科書に残らないけど心に残る歴史』から一部抜粋、再構成したものです。
倒れそうなほど疲労困憊
「うぎゃあ!うぐぐ……痛いっ!痛い!」
手術の部屋から患者の悲鳴があがる。つい、さきほど血を流しながら、運ばれてきたばかりの患者だ。
「長くなるかしら……」
加恵は何もできないもどかしさを覚えながらも、手術が無事に終わることを祈るばかりだった。しばらくして、夫の華岡青洲(はなおか・せいしゅう、江戸時代後期の外科医)が部屋から出てきた。汗びっしょりで、今にも倒れそうなほど疲労困憊しており、うつむいたまま、居間へと入っていく。
「お疲れさまでした」
そう声をかけても、加恵が出したお茶も飲まずに、青洲はただ腕組みをして、目をつぶっている。
「手術はうまくいきませんでしたか」
青洲はようやく加恵がいることに気づいたような顔をして、「いや、手術はなんとかうまくいった」と言うと、少し頬を緩めたが、すぐに難しい顔をした。
「しかし、あれだけ暴れられると、手術に時間がかかって、患者の身体への負担が大きくなってしまう」
患者の悲鳴を聞くだけで、加恵などは身がすくんでしまう。その点、青洲の母、於継(おつぎ)は肝が据わっている。以前、せめて手術の準備だけでも手伝おうと、まごまごしていると「手を出してはだめ!」と一喝されてしまった。青洲は医師の父からこの医院を継いでいる。加恵にとって、於継は医師の妻として見習うべき存在だった。
「やはり麻酔薬だ。麻酔さえあれば、状況は変えられるんだが……」
ようやくお茶に手をつけた青洲が天井の角をにらみながら、自分を奮い立たせるように言った。
「麻酔薬……ですか?」
「ああ、麻酔薬さえあれば、眠っている間に手術は終えられる。患者は激痛に耐えなくていいし、医師は手術に集中できる」
そんな魔法のような薬があるわけがない。初めはそう思ったが、青洲の熱弁を聞いているうちに、可能なのかもしれないと思えてきた。必要なのは「マンダラゲの花」。強い毒性を持つが、それゆえ「使い方次第で、薬にもなる」と青洲はいう。
その日からというもの、青洲は犬や猫を使って実験を繰り返した。マンダラゲの花で麻酔薬を作り、犬に飲ませると、まもなくして眠りについた。
「あなた、眠ってるわ!」
「うむ、だが……」
青洲が犬の足にプスリと針を刺すと、キャインと鳴いて、その場から慌てて逃げてしまった。
「この程度の刺激で起きてしまうようじゃ、とても手術はできない。かといって、あまり刺激が強すぎると死んでしまうしな……」
何匹かの犬や猫は死んでしまった。それでも青洲はさまざまな薬草を混ぜながら、その量の割合を変えて研究を進めていく。その姿を加恵はそばで見守ることしかできなかった。
「センキュウにトウキ、それにビャクシも混ぜてみるか……」
病室からはいつもの叫び声
そんな実験を行っている最中にも、患者は運び込まれてくる。家族は必死の形相で青洲に頭を下げる。
「先生、お願いします!」
「わかりました。ちょっと我慢してくださいね」
青洲は患者に縄の切れ端を渡して、それをくわえさせる。少しでも痛みに耐えられるようにするためだ。
「グググ…… ぎゃっ、痛い!やめて……やめてくれー!」
病室からいつもの叫び声が聞こえてくる。思わず耳をふさぎたくなる加恵だったが、唇をぎゅっと噛んで、患者の叫び声を聞いていた。夫は患者のそばでこの悲痛な叫びを聞きながら、手術に励んでいる。そう思うと、自分だけが耳をふさぐわけにはいかないような気がしたのだ。
だけど、もし、こんな思いをせずに患者が手術を受けられるならば、どれだけ良いことだろう……。加恵もまた青洲と同じく麻酔薬の実現を夢見るようになった。
青洲の妹、於勝(おかつ)が医院を訪れたのはそんなときである。青洲が横たわった妹の胸を触診すると、大きなしこりがすぐに見つかった。乳がんだ。
「どうして、こんな大きさになるまで放っておいたんだ!」
青洲が声を荒らげると、妹はふっと笑って言った。
「乳がんですもの。助からないでしょう。ねえ、兄さん、だから、私の身体を使って。胸を切り開いて、がんの正体を突き止めて」
「何を言ってるんだ……痛みと出血で死んでしまうぞ!」
「もう今だって痛みでどうしようもないの……お願い」
加恵は部屋の外でその声を聞いていると、そばにいる青洲の母、於継が「於勝……」と泣き出した。強く見えても、娘の前ではただ一人の母親なのだと、加恵もまた涙ぐんだ。
青洲が病室から出てくると、於継が駆け寄る。
「何とかできないのかい」
「あれだけ大きなしこりを取り除くには、麻酔薬がなければ、手術はできない」
青洲は力なくそう言って「少しでもそばにいてやってくれ」というのみだった。数日後、痛みに苦しみながら、於勝はこの世を去ることとなった。
それからも青洲は実験を繰り返し、動物ならば確実に眠らせることに成功していた。どこを刺そうが熟睡して動かない犬を見て、加恵は興奮気味に言った。
「あなた、これだけキリで突っついても、起きないわ!麻酔薬ができたのね!」
青洲は喜びもせずにまた腕組み
だが、青洲は「うむ」と言ったきり、喜びもせずにまた腕組みをして考え込んでいる。その様子を黙ってみていた、於継が口を開いた。
「ついに、このときが来ましたね。青洲、私を使いなさい」
「母さん……」
ぽかんとしている加恵をよそに、於継が手術の部屋に入っていく。
「加恵さん、あとのことはよろしくね」
加恵が「な、何をおっしゃってるんですか!」と慌てると、於継は何気ないふうを装って穏やかに言った。
「もう動物実験は終わり。ここからは人に効くかどうかを試さないと。青洲、そうでしょう?」
「そうだけど……だめだ。これは危険な実験なんだ」
「だからこそ、私がやらないでどうするんですか。もう十分生きたからよいのです」
加恵は「そんな……」と思わず絶句しながら、嫁入りしてから於継と過ごした日々が自然と思い返された。厳しかったけれど、医師の妻としてあるべき姿を教えてくれた於継に、加恵は憧れさえ抱いていた。
そして今、誇り高き姿で於継は布団の上に座っている。
「さあ、さっき犬に飲ませたその薬の量を調節しなさい。ここまでよくやったじゃないの。もう少しよ」
青洲が薬を持ったまま逡巡していると、加恵がその横に布団を敷き出した。
「何をしてるの!」
於継が慌てると、加恵は穏やかな顔で言った。
「お義母さん、実験台には私がなります。私のほうが、もしもの時にでも助かる可能性があると思いますから」
「加恵!お前一体、何を……」
「そうですよ!あなたはこれからの将来が……」
「将来があるから、です。だから、私がやらないといけないんです。これからの医学を発展させるために、私を使ってください」
加恵は2人からどれだけ止められても、頑として布団から動かなかった。これまで、医師の妻として何をすべきか、ずっと考えていた答えがようやく出たと、加恵の決心は固かった。
「加恵さん……本当にあなたがやるの……」
心配そうな於継に、加恵はにっこり微笑んだ。
「大丈夫です。動物たちにはうまくいっているのですから。さあ、あなた。於勝さんのような思いを、もう誰にもさせないために」
加恵の強い思いに、青洲も心を動かされて意を決する。これまでの実験で、青洲は麻酔薬への自信を深めていた。
「わかった。少しでも異常があれば言ってくれ。絶対に死なせはしない」
「はい。私のことは心配しないでください」
加恵が、青洲から手渡された薬を一飲みした。しばらくすると、意識が遠のいていき、周囲の音が聞こえなくなっていった。
3日も眠っていた加恵
目を覚ますと、青洲と於継が自分の顔をのぞき込んでいる。於継は感極まって泣き出し、青洲がその手を握った。
「よし、目を覚ましたか!」
「私……少し眠っていましたか?」
「ああ、3日も眠っていたんだ。具合はどうだ」
「3日も……体調は何ともないわ」
「そうか、成功だ!」
これで麻酔を使った手術ができる、と3人は抱き合って喜んだ。とはいえ、患者に使うには、まだ実験データが不足している。母の於継も実験台に加わり、何度か実験が繰り返されることとなった。
だが、加恵が2回目の実験に挑んだときのことだ。目を覚ますと、あたりは真っ暗である。
「よかった、意識が戻ったか。これで麻酔薬は完成……」
暗闇のなか、青洲の声だけが聞こえてくるので、加恵は聞いた。
「今日は何日目の夜ですか」
場がざわめき立つのを加恵が感じたとき、於継の叫び声が部屋に響く。
「夜ですって!今は昼間よ、加恵さん!」
「まさか、お前、目が……」
視力を失ってしまった加恵の姿に、青洲は号泣した。
「すまない!おそらくソウウズの毒が目を……」
於継も涙で声にならないなか、加恵はにっこりとほほ笑んだ。
「いいんですよ。これで多くの人が救われるのですから。あなた、実験を続けてください」
加恵は、これまで病室でのたうち回る何人もの患者の声を聞いてきた。於勝のように亡くなった人もいる。そして、実験では動物の命も失われた。そのたびに、涙する青洲の姿を見てきたのだ。目が見えなくなったことくらいで、嘆き悲しむに値しない。加恵は心の底からそう思っていた。
完成した麻酔薬「通仙散」
大きな犠牲を払いながらも、青洲は麻酔薬を完成させる。薬には「通仙散(つうせんさん)」と名づけた。
そして、ついに来るべきときがくる。文化元(1804)年10月13日、青洲は通仙散を用いて、世界初の全身麻酔による乳がんの手術に成功した。
「加恵、玄白先生から手紙が届いたぞ!」
「まあ、なんて書いてあるのですか」
「なんでも手術について詳しく教えてほしいらしい。あの玄白先生が私を……」
「よかったわね、あなた。さあ、午後からまた一人、手術ですよ」
「ありがとう、加恵、ほんとうに……」
不治の病とされていた乳がん。それだけに、青洲の成功を知った乳がんの患者が、全国各地から医院に訪れることとなった。青洲は76歳で亡くなるまで、実に156人にもわたる乳がんの患者を治療したと記録されている。
(真山 知幸:著述家)
※東洋経済オンラインの2021年12月17日の記事(https://toyokeizai.net/articles/-/476152?utm_source=gunosy-kddi&utm_medium=http&utm_campaign=link_back&utm_content=article)より抜粋
今の医学のベースは、こういった人々の「命がけ」の精神が無ければ成り立っていなかったと思います。
心が震えます。
抜粋記事に出てくる、「マンダラゲの花」は、チョウセンアサガオのことを指しているようです。
☝の養命酒の記事にも、華岡青洲のことが取り上げられており、”曼陀羅華(マンダラゲ)とはナス科のチョウセンアサガオのこと”という記載があります。
また、日本麻酔科学会のシンボルマークに、チョウセンアサガオが採用されています。(以下)
麻酔とチョウセンアサガオの関係性については全く知らなかったので、とても勉強になりました。