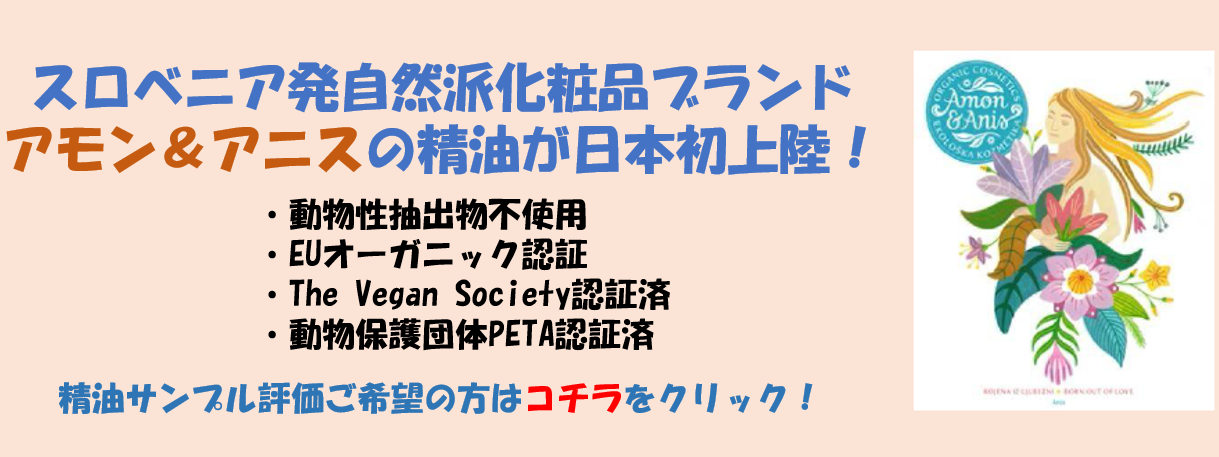世間はコロナ報道の真っ只中ですが、もう気が付くと4月中旬に差し掛かるタイミングになってきて、5月~6月のジャーマンカモミールの時期、及び、6月~7月のラベンダーの時期が目前に迫ってきています。
ハーバリストにとって、この時期にアクティブに動き回れないのは、非常に悔しいところではあるのですが、ここはグッとこらえ、今後の中・長期の自分自身の成長につながる行動を心を落ち着けて取り続けていくタイミングと捉えるようにしています。
現在のように、家にいる時間が増えるタイミングこそ、じっくりと「歴史」に意識を向けることは、今の事象を分析する上で有効だと思います。例えば、感染症の歴史の中で最もメジャーと言ってもいい「ペスト」について、過去のパンデミックの性質、致死率、現在のペストの状況を流れで追っていくと、今後の世界の予測をする上で参考になるような気がします。
”腰を据えて学ぶ”という点で、北海道のラベンダー栽培の歴史に関する非常に興味深い特集記事があったので、今日・明日はそれを取り上げたいと思います。
富良野ラベンダー物語1〜海を越えた友情が咲かせた花〜

Shawn.ccf/Shutterstock.com
今や北海道を象徴する花として知られるようになったラベンダー。太平洋戦争直後にニセコ町で最初に栽培されて以降、その香りに魅せられた人々を巻き込んで、波乱万丈の歴史を繰り返し、さまざまなドラマを生んできました。日本のラベンダー栽培の激動の軌跡をたどります。
ラベンダー栽培発祥の地
cjmac/Shutterstock.com 北海道で最初にラベンダーの大量栽培を始めたのは、虻田郡ニセコ町の十数戸の農家。太平洋戦争直後の1947(昭和22)年、ラベンダーを新たな畑作物として導入し、エッセンシャルオイル(花精油)の生産に取り組んだ。
ところが──。
ニセコ町は日本海に近く、冬に降る雪はいわゆる湿雪。水分が多く含まれているので、積雪が進むにつれて重くなる。そのためラベンダーは雪の下で幹が裂けたり枝が折れたりして、春になっても樹勢を回復することができず、結局は枯死してしまう。詳しい記録は町にも残っていないが、「あまりにも雪害がひどいので、1964年までには栽培から撤退したようです」と町役場の職員は話す。
わずか17年という短命に終わったニセコ町でのラベンダー栽培。
しかし、ニセコ町は現在もラベンダーを「町の花」に定めている。
北海道におけるラベンダーの栽培はその後も波乱万丈の歴史を繰り返し、さまざまなドラマを生んでゆく。その激動の軌跡をたどってみることにしよう。
マルセイユ、東京
Alla Greeg/Shutterstock.com 1937(昭和12)年4月、フランスのマルセイユ港で、約5kgのラベンダーの種子が貨物船に積み込まれた。この荷の送り主は、マルセイユの香料商アントワン・ヴィアル。種子の行き先は日本で、受取人は東京・日本橋の香料製造業者、曽田政治。
マルセイユを出た船は地中海を南下してスエズ運河に入り、紅海、アデン湾を経て波高きインド洋を東へと進み、セイロン島のコロンボに寄港。その20日後にシンガポールに着き、香港、上海、神戸港、大阪港を経由して、マルセイユを出港してからおよそ40日後、横浜港に到着した。
こうして長い旅をしてきた約5kgのラベンダーの種子──。その種子が北海道へとさらに旅をする。そして栽培の歴史の幕が開くことになるのだが、そのきっかけをつくった重要人物が曽田政治(1890〜1977)。彼はいったいなぜ、ラベンダーの種子を輸入しようと思い立ったのか?
感激の対面
ネット上では、政治がフランスを旅行した際、美しいラベンダー畑を見て種子の輸入を思いついたという説が紹介されているが、これは勝手な空想によるまったくの謬説。政治は戦前には海外に行ったことがなく、初めてヨーロッパの香料業界の視察旅行に出かけたのは1961年。このとき彼はマルセイユで、かつてラベンダーの種子を送ってくれたアントワン・ヴィアルと感激の対面をしている。
海を超えた友情
Igor_C/Shutterstock.com 2人はそれまで、香料の取り引きで30年近い付き合いがあったが、電子メールなど影も形もなく、国際電話も今日のようには普及していなかった時代。お互いのやり取りは取り引きのたびに交わす英文の書状だけに限られていた。しかし、2人は長年の交流を通じて深い信頼関係で結ばれていた。
その信頼関係がなければ、ラベンダーの種子が日本に送られることも、北海道で花を咲かせることもなかったに違いない。というのも、ラベンダーの種子は農産物の一種で香料ではなく、本来は香料商が取り扱う品目ではない。だから、アントワン・ヴィアルは政治からのラベンダーの種子を送ってほしいという筋違いの依頼を断ってもよかったのだが、しかし彼は断らなかった。
というより、ヴィアルはむしろ、この依頼を断ったら、曽田政治という東洋の顧客との間に培ってきた長年の信義に反すると考えたのだろう。彼は愛車を駆ってマルセイユの北に広がるプロヴァンス地方の高原地帯の村々を走り回り、そこに点在するラベンダー農家を一軒一軒訪ね歩いて、ようやく約5kgの種子を集め、それを政治に送ってくれたのだった。
今日まで営々として続いている北海道におけるラベンダー栽培──。その歴史のそもそもの始まりに、このような海を超えた友情があったということは、記憶しておくに値するエピソードだといってよいだろう。
歓談のひととき
マルセイユの高級住宅地にあるヴィアルの自宅マンションを訪ねたとき、政治はその頃急速に栽培面積を拡大しつつあった北海道のラベンダー畑の写真を何枚か持参していた。それを見たヴィアルは、心底驚いた様子だったという。依頼に応えて種子を送りはしたものの、日本でそんなに栽培が盛んになるというところまでは想像していなかったのかもしれない。政治とヴィアルのこの日の歓談は、途切れることなく何時間も続いた。「初めて会ったという気が、まったくしなかった」と政治は自伝に感慨深げに記している。
夜学に通う少年
Fabulous mist/Shutterstock.com さて、時は明治の末、日本の香料業界の黎明期にさかのぼる。東京・日本橋本石町の香料店、松沢常吉商店で一番下っ端の店員として働きながら、夜は神田の英語学校に通っている少年がいた。若き日の曽田政治である。
彼は家が貧しかったため、15歳のときに新潟県の中頸城郡黒川村大字水野という草深い山里から上京。働き口を2度ほど変えた後、松沢商店の店員となったのだが、もともと頭脳はすこぶる明晰、性格は温厚で真面目。そんな政治を見込んで、松沢商店の香料部門の責任者、松沢覚三が彼を英語学校に通わせていたのである。
当時、日本の香料店は、かねてから英国やスイス、オランダなどの香料会社から盛んな売り込み攻勢をかけられていた。ところが、どの店にも外国語のできる従業員がいない。そのため、ろくな応対ができず、せっかくの商機をみすみす逃すという結果になっていた。
松沢覚三が目をつけたのはそこだった。もし、外国語のできる従業員がいて、ヨーロッパの香料会社と直接取り引きができるようになれば、横浜の外国商館に支払っている輸入事務代行の手数料がそっくり浮く。その分を売り値に反映させ、価格を引き下げれば今よりもっと多くの顧客を獲得することができ、大きな利益を上げることができる。覚三はそう考え、日頃からその明敏さと性格のよさを見抜いていた政治に白羽の矢を立て、自ら学資を負担して英語学校に通わせることにしたのだった。
独立開業
神田錦町の英語学校で4年間学んだ政治は、簡単な会話もできるぐらいの英語力を身につけ、早速、スイスの大手香料会社と直接取り引きの契約を結ぶことに成功。そのほかにもヨーロッパの香料会社と折衝して目覚ましい成果を挙げ、英語を学ばせてくれた主人、覚三への十分な恩返しを果たした。
1915(大正4)年春、政治は松沢商店での7年間の奉公を終えて独立。日本橋鉄砲町に「曽田香料店」を開業した。弱冠25歳での独立だった。
関東大震災
その後、店は順調に発展。開業から6年後には大阪に出張所を開設するまでになったが、そんなとき未曾有の災害が政治を襲う。
1923(大正12)年9月1日に突如として発生した関東大震災──。
倒壊した家屋から出た火が、折からの北東の風にあおられて日本橋一帯を焼き尽くし、政治の店もあっという間に焼失。在庫の香料もほとんどが灰燼に帰し、わずかに焼け残ったのは大八車に積んで、至急、皇居前広場に運んだごく一部の高級香料だけ。被害の甚大さに、政治も一時は店の再建を諦めたほどだった。
だが、政治は家族とともに避難先を転々としながら、資金繰りと建築資材の確保に奔走。被災からわずか2カ月後、元の場所に2階建ての住居兼店舗を新築して営業を再開する。
同業者の多くが瓦礫の山を前に茫然と手をこまねいているなかでの鮮やかな再起だった。
これを機に、香料業界における曽田香料店の存在感と信用度は一挙に高まり、資生堂、ライオン歯磨、花王石鹸といった大手取引先との関係が一層緊密になってゆく。
日本経済の再建へ
ところが、予想もしていなかった苦難が、またしても政治を襲う。震災当時、日本の政治状況はきわめて不安定で、大打撃を受けた経済の再建に取り組む安定した政権がなかなか誕生しなかった。が、三党派連立による加藤高明内閣がようやく成立。経済の復興を担う大蔵大臣には浜口雄幸が就任した。
浜口はライオンのようないかめしい風貌と謹厳実直な人柄で知られ、当時の政治家のなかでは大衆に最も人気のある人物だった。政治も実は、隠れ浜口ファンの一人だった。だが、彼の浜口に寄せる期待は無惨に裏切られてしまう。
贅沢品輸入税引上法
barmalini/Shutterstock.com 日本経済の再建のためには、何よりもまず国内産業の育成を推進することが急務だった。また一方では、海外からの輸入を極力抑制し、外貨を節約することが肝要だった。そこで浜口は、海外から輸入される贅沢品に「10割」の関税を課すという思い切った政策を立案。そのための法案を国会に提出し、早期の成立を図った。
政治たち香料業者にとっては、まさに青天の霹靂だった。さまざまな香料を原料として使用している香水や化粧品、石鹸、歯磨き粉などの製造業界にも激震が走った。浜口が国会に提出した「贅沢品輸入税引上法」では、海外から輸入している香料のほとんどすべてが贅沢品として10割関税の課税対象品目に指定されていたからである。
10割の関税が課せられるということは、これまで1kg1,000円で輸入できていたものが、いきなり2,000円にハネ上がるということであり、贅沢品輸入税引上法は、実際は「輸入禁止法」に近い。
必死の陳情
香料業界と香水や化粧品、石鹸、歯磨き粉などの製造業界は合同の陳情団を結成。連日、国会に出向いて、浜口が提出した法案の撤回を求めた。
その結果──。
20数種類の香料については、何とか10割関税の課税対象品目から除外してもらうことができた。しかし、その他の800種近くある香料はすべて贅沢品として10割関税の対象となり、事実上、輸入ができなくなってしまった。
倒産、廃業の危機
贅沢品輸入税引上法は国会でさしたる論議も行われることなく成立し、浜口の蔵相就任から1カ月半後の1924(大正13)年7月から施行された。政治の店はその直後から日を追うにつれて売り上げが激減し、急速に経営が悪化。倒産、ないしは廃業まで考えなければならない事態に追い込まれた。
政治がフランスからラベンダーの種子を輸入しようと思い立ったのは、このときの苦しい経験があったからにほかならない。
香料の国産化
Shawn.ccf/Shutterstock.com 何とか店を救おうと金策に走り回りながら、政治はこう考えるようになった。
「我々が香料をすべて海外からの輸入に頼り切っているから、こういう危機を招くのだ」
そして、たとえ今回の危機をどうにか乗り越えたとしても、ひとたび何か変事があれば、再び同じようなことが起きるに違いない。それを避けるためには、どうすればいいのか?
政治の脳裡に、天啓のように閃いた考えがあった。それは香料を日本国内で生産し、海外からの輸入への依存度を低めていく、即ち香料の国内自給体制を確立するというアイデアだった。
「そうだ! 香料は今後、可能なものから順次、国産化していかなければならない!」
こうして政治は、旧知のマルセイユの香料商アントワン・ヴィアルにラベンダーの種子を送ってほしいという英文の書状を書くことになる。このとき政治は、ラベンダーオイルの国産化という大きな夢に向かって、歩を進め始めていたのである。
Credit
文/岡崎英生(文筆家・園芸家)
早稲田大学文学部フランス文学科卒業。編集者から漫画の原作者、文筆家へ。1996年より長野県松本市内四賀地区にあるクラインガルテン(滞在型市民農園)に通い、この地域に古くから伝わる有機栽培法を学びながら畑づくりを楽しむ。ラベンダーにも造詣が深く、著書に『芳香の大地 ラベンダーと北海道』(ラベンダークラブ刊)、訳書に『ラベンダーとラバンジン』(クリスティアーヌ・ムニエ著、フレグランスジャーナル社刊)など。※Garden Storyの2020年1月21日の記事(https://gardenstory.jp/stories/38493)より抜粋
この一連のストーリーをみて、「そういうことだったのか!」と、震えあがりました。
個人的には、曽田香料の創始者の曽田政治氏のことについて細かく記載があることに感動しました。
過去に、曽田香料が絡む記事を幾つか取り上げたことがあります。
【過去の参考記事:曽田香料が運営する香料植物園(小豆島)の存在を知ったことで、”ローズゼラニウム”と”小豆島”の繋がりが明確になりました。】
【過去の参考記事:九州旅行に行ったら必ず行ってみたい日本最古のハーブ園「開聞山麓香料園」】
【過去の参考記事:ハーブの女王『ラベンダー』について様々な角度からシンプルに纏めた記事が楽しめました。】
日本のハーブ栽培の歴史は、曽田政治氏の存在無くしては語ることができないということがはっきりと認識できました。
明日も本編の続きを取り上げます。楽しみです。