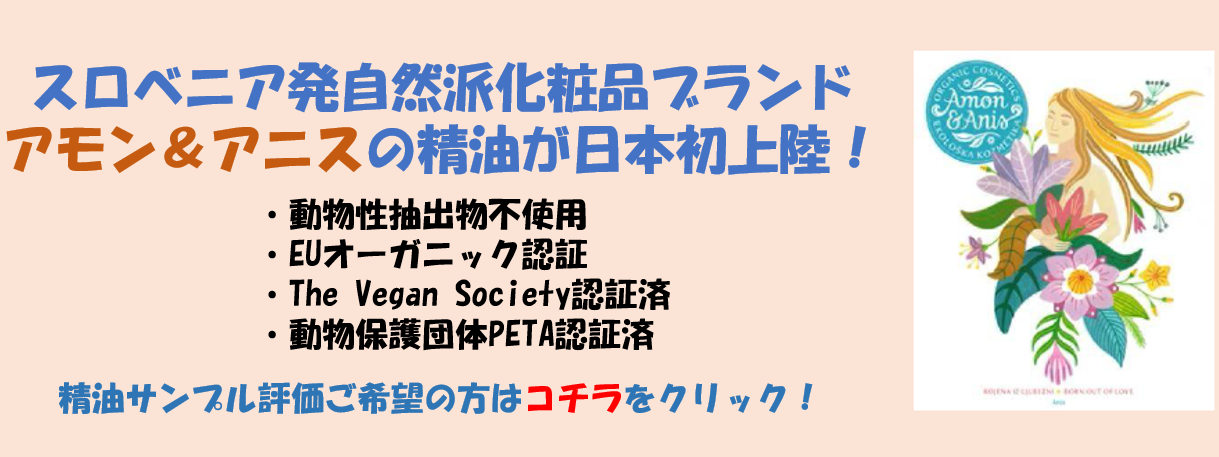日々ハーブと親しむ人達にとって、イギリスの貴族の家系に生まれ、来日してからハーブと共に暮らす生活を実践してきたベニシア・スタンレー・スミスさん(ハーブ研究家)のライフスタイルに憧れを持つ人は多いと思います。
私もその一人であり、ベニシアさんについての情報にはいつもアンテナを張っているので、過去に何度か弊ブログの中で取り上げたことがあります。
【過去の関連記事:「ベニシア・スタンリー・スミスさんの講演会」開催告知で、”やっぱりそうだったのか”と思った情報について】(2018年9月1日)
【過去の関連記事:『京都大原の庭とキッチンから ベニシアさんの手づくり暮らし展』へ足を運び、感じたことについて】(2019年3月8日)
昨年、「ベニシアさんの手づくり暮らし展」へ足を運んだ時に、ベニシアさんは目の病気にかかっていることを知り、その事に対するベニシアさん自身の言葉(以下太字)が、動画で流れていたのが非常に印象的でした。
「人生はいい事ばかりではなく、そうじゃないこともたくさんある。私の目の病気も、私自身への何かしらのメッセージであって、私自身の足りないことを教えてくれていると思うんです。」
ベニシアさんのその謙虚さに心を打たれ、さらにベニシアさんのファンになりました。
その後、ベニシアさんの目の病気が気になっていたのですが、本日、非常にポジティブなニュースが舞い込んできましたのでご紹介します。
ベニシアが70歳のデビューアルバムで歌う「スカボロー・フェア」
ベニシア・スタンリー・スミス(70)という女性をご存じだろうか。イギリス出身ながら、京都の市街地から離れた大原という山間の町で、築100年もの古民家に暮らすハーブ研究家だ。自然に囲まれた暮らしの中から花や植物を育てたり、ハンドメイドのハーブティーや家庭料理を披露したり、ものづくりをする知人の仕事場を訪ね歩いたりする姿を、NHKEテレの冠番組「猫のしっぽ カエルの手~京都 大原 ベニシアの手づくり暮らし」を通じて見たことがある人もいるだろう。夫であるカメラマンの梶山正ら家族とともに穏やかに過ごす京都・大原でのライフスタイルを紹介する書籍も多い。
【ベニシアの京都・大原での暮らしぶりが伝わるジャケット写真はこちら】 京都に根を下ろして約40年、関西訛りの日本語もすっかり流暢なベニシアが、ミュージシャンとして初めてのアルバム「音楽という贈り物」をリリースした。70歳のデビュー作品集に収められているのは5曲。ベニシアによるオリジナル曲は1曲でカヴァーが中心だが、単なる雰囲気ありきのアルバムとは違う。
とりあげられているカヴァー曲は、ドノヴァンの「Colors」、カーペンターズの「Sing」、サイモン&ガーファンクルの歌声で知られるイギリス民謡の「スカボロー・フェア」。いずれもベニシアの飾らない歌が味わえる、素朴でフォーキーな仕上がりだ。決して歌い手として達者ではないものの、つらかったことも含め豊かな人生経験が刻まれた歌声には心を揺さぶられる。
1950年ロンドン生まれのベニシアは、カーゾン侯爵(初代スカーズデール子爵)という英国貴族の血をひいている。名門校で学び、19歳でイギリスを離れて陸路インドへと向かった。そこから鹿児島へとたどり着き、京都に安住するまでの波乱万丈な半生は、これまで彼女の自著でも語られてきた。古い日本家屋を丁寧にメンテナンスしながらゆったりとした時間を過ごす日々は、都会であくせく働く者たちにとっての憧れでもあるだろう。だが、今回リリースされた「音楽という贈り物」で伝えられるのは、彼女自身の民族ルーツ=英国への情緒あふれる郷愁の思いだ。
それを象徴するのがカヴァーの1曲「スカボロー・フェア」。60年代にサイモン&ガーファンクルがとりあげ、ダスティン・ホフマン主演映画「卒業」の劇中でも流れたためアメリカの音楽と思われがちだが、もともとはイギリスの伝承歌が発祥とされている。主にイギリスなどヨーロッパの各地に言い伝えられてきた寓話や民話をもとに、反復やリフレインを用いた形式で独唱、朗読されるこうした伝承歌のことを「バラッド」と呼ぶ。ポップスなどでテンポの遅い曲調を指す「バラード」はこの言葉から派生したものだ。
「スカボロー・フェア」はまさにそうした「バラッド」を代表する歌の一つ。作者不詳とされる曲の多くは、誰からともなく歌い継がれてきたもので、現在70歳のベニシアも、小さい頃に自然とこれらの「バラッド」を耳にして育ったのだろう。
スコットランド出身のシンガー・ソングライター、ドノヴァンの「Colors」をとりあげているのも、おそらく偶然ではない。60年代に「サンシャイン・スーパーマン」「ハーディー・ガーデイー・マン」といった多数のヒットを放ち、日本でも人気を獲得していたドノヴァンは、「バラッド」の伝統を受け継ぐミュージシャンだ。ベニシアがティーンエージャーの頃、すでに成功をつかんでいたドノヴァンは、彼女にとって歌で母国を思い出させる存在なのかもしれない。そらで歌っているかのような自然な歌い方が、彼女の遠い記憶を引き寄せている。
音楽経験はほとんどない。だが、10代の寄宿学校時代、聖歌隊で歌っていたというベニシアにとって、歌を歌うということ、音楽に触れるということは、生活を豊かにしてくれるものだった。聖歌隊のオーディションでは、イギリス民謡「ラベンダーは青い(ラベンダーズ・ブルー)」を歌ったという。本作のために寄稿したベニシア本人のエッセーには、次のようにつづられている。
「朝礼で聖歌隊オーディションの結果が発表された。私の学年からは、ターシャ、ダイアナ、そして私の三人が選ばれた。みんなが大きな拍手をしてくれた。拍手がやむと、校長先生は笑顔で続けた。『もうひとつ発表します。今年のマタイのソロを歌うのは、ベニシア・スタンリースミスです』。クラシック聖歌の傑作といわれるマタイ受難曲は、マタイ福音書26章と27章にヨハン・セバスチャン・バッハがメロディをつけた、キリスト教オラトリオである。全校からの喝采に、私は笑顔で応えながら、信じられない気持ちだった」
このアルバムは、ただのノスタルジーではない。「スカボロー・フェア」の歌詞に「パセリ、セージ、ローズマリー&タイム」というくだりがあるが、現在の京都・大原の自宅の庭でハーブなどの植物を育てる日々を意味するものでもある。「バラッド」を通じて目に浮かぶイギリス時代の記憶は、そのまま今の暮らしの光景につながっているのだ。決して昔を懐かしんで歌っているだけではない。
実際、このアルバムにはベニシアの近所に暮らす元「渋さ知らズ」の横山ちひろがピアノとアレンジで、同じく京都出身京都在住のシンガー・ソングライター、元「くるり」の吉田省念がギターとチェロで参加している。京都での暮らしで知り合った仲間が、ベニシアの温かな人柄を伝えるべく、さりげないサポートしているのが嬉しい。
このデビュー・アルバムは、ベニシア自身のパーソナルな思い出や充実した今の暮らしを、歌と言葉と生楽器による奥ゆかしい演奏で叙情的に捉えた作品だ。同時に、伝承歌の魅力を改めて伝えている。「バラッド」という音楽は個人の喜びや悲しみだけでなく、多くの人々の笑顔や涙にも寄り添う。時代も地域をも超えるのである。(文/岡村詩野)
※2020年1月21日のAERAオンライン限定記事(https://dot.asahi.com/aera/2020012100018.html?page=1)より抜粋
私はこの記事を見たときに、目の病気にかかり、自分に足りないものは何か?と模索した先の一つの答えなのではないか、と薄っすらと感じました。
多くのベニシアさんの著書には、「貴族社会に疑問を感じ、インドを旅し、日本に辿り着いた」という主旨の記載があります。
どこか、ベニシアさんの中で、「自分のルーツに背を向けていた罪悪感のようなものがあったのでは?」 ということが、上記の記事を見て想像しました。
ご自身のルーツと深く向き合った結果として、「音楽という贈り物」という作品が生まれたのかもしれないと勝手ながら思いました。
記事中の「スカボローフェア」の歌詞に、パセリ、セージ、ローズマリーにタイム(Parsley, sage, rosemary and thyme)というくだりがある件ですが、「スカボローフェア」自体が、とても深いメッセージが込められた歌であることを知り、そのことを取り上げたことがあります。
【過去の参考記事:【パセリ、セージ、ローズマリーにタイム】サイモン&ガーファンクルとハーブの意外な接点】
ベニシアさんの今の胸中が、「音楽という贈り物」の中のベニシアさんの歌声を聴くことで、深く伝わってくるように思います。
私自身もじっくりと聞いてみたいと思います。