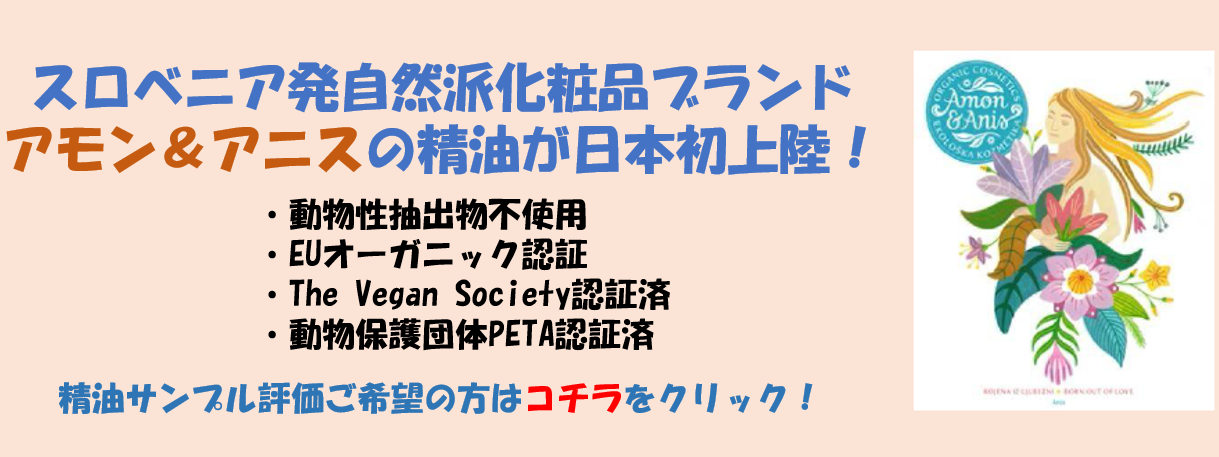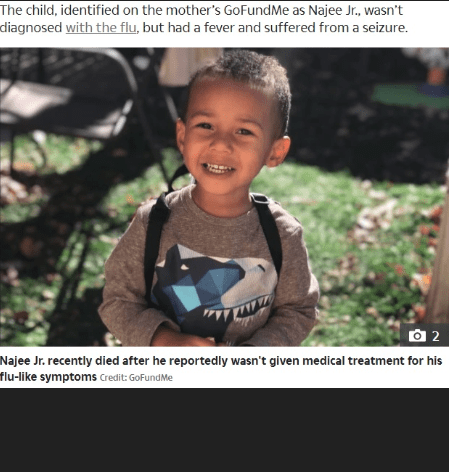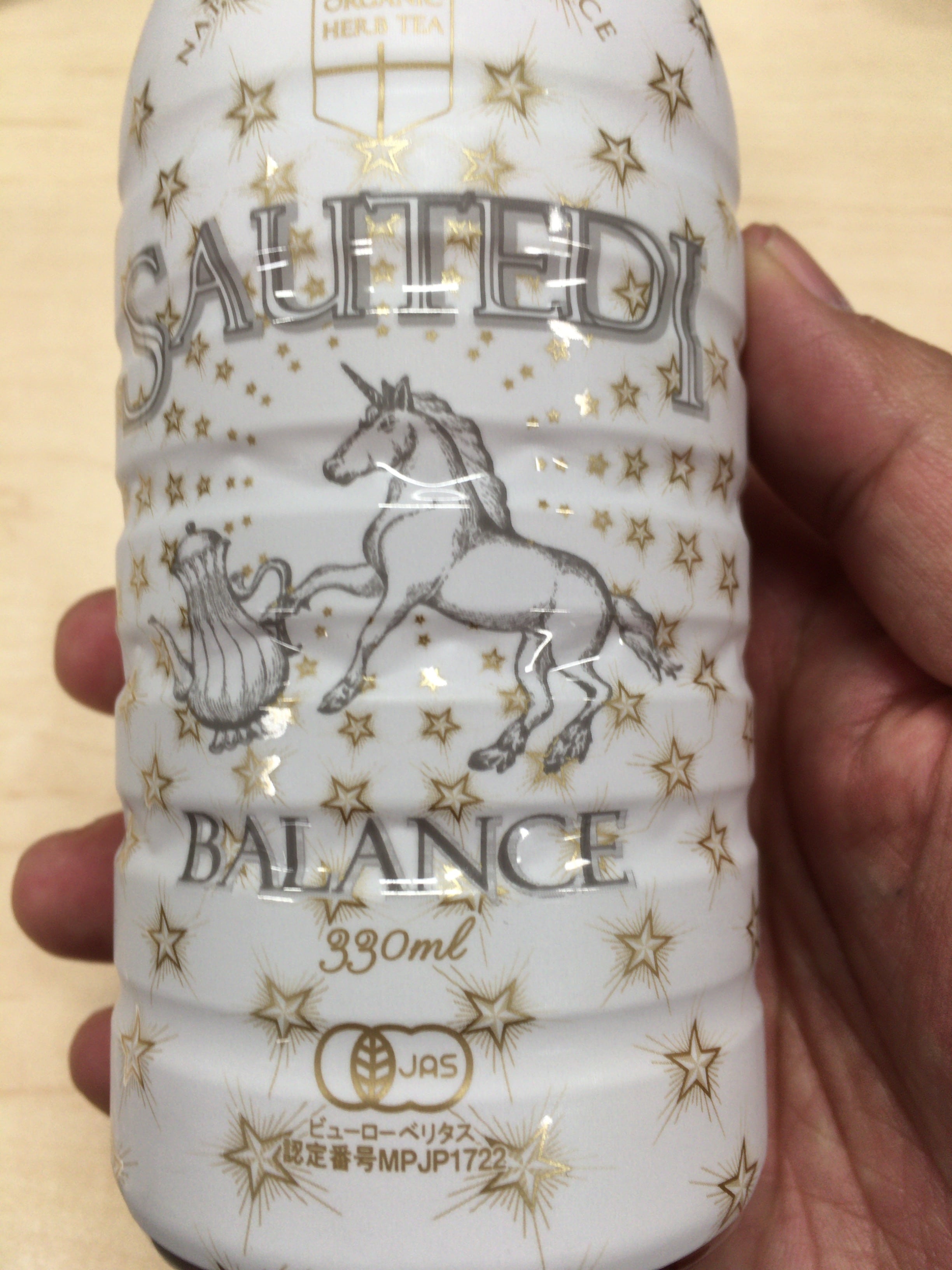私自身、徐々にハーバルライフを楽しむ時間を取り戻すように意識している中で、先々月、地元のハーブコミュニティーに所属し活動を開始しました。
ハーブ畑の中で、ハーブを摘み、様々なハーブの香りを楽しむなかで、自分が忘れかけていた楽しさの感覚が蘇ってきているという実感があります。
ハーブに囲まれているだけで、自然に笑顔になっていて、心のテンションも知らぬ間に上がっていることに気付き、改めて自分にはハーブが必要なことを自覚しました。
No Herb No Lifeです。
今日は中国の香りに関する情報を取り上げたいと思います。
香りをまとう「自然療法」 中国で薬草香囊づくりが人気に
 北京・王府井近くの協和時光文化クリエーティブショップで、来店者が手づくりした香囊=2025年7月4日撮影・資料写真(c)CNS/劉遠
北京・王府井近くの協和時光文化クリエーティブショップで、来店者が手づくりした香囊=2025年7月4日撮影・資料写真(c)CNS/劉遠【9月19日 CNS】夏の盛り、中国・北京市や広州市(Guangzhou)、上海市、南京市(Nanjing)など各地の薬草館や博物館、専門店で、薬草を使った香囊(香り袋)や香珠(薬草を練り込んで作る数珠状のアクセサリー)の販売・体験イベントが盛んに行われている。香囊や香珠は、清々しい香りを放ちながら体調を整えるとされ、身につけたり部屋に掛けたりすることで、鼻や皮膚を通じて体内に作用する。中医学(中国医学)においては「自然療法」「衣冠療法(薬草をしみ込ませた袋や飾りを衣服や装身具として身につけ、その香りや成分で体調を整える中医学の伝統療法)」の一種とされる。
「香囊のレシピは32種類あり、気分を落ち着けたり、疲れを和らげたり、頭をすっきりさせたり、気の巡りを整えたり、さらには蚊よけの効果もあります」。北京・天安門広場(Tiananmen Square)からほど近い胡同(路地)にある制香店「梓霖堂」の店長・張偉(Zhang Wei)さんはそう説明する。店では香囊1つ33元(約680円)、2人組なら53元(約1092円)で体験でき、1度に30個を作って自分用や贈り物にする人もいるという。
張さんは中国北派薬香づくりの第7代継承者で、16年前から香囊づくりの体験を提供してきた。季節によって人気の配方は変わり、春は気の流れを整えるブレンド、夏は蚊よけや暑さ対策、秋冬は鼻炎や風邪予防の香囊がよく選ばれるという。
「店に入った瞬間から香りに包まれ、自分で調合した「梨の香」は甘く清らかで、沈香と白檀の組み合わせは心を静めてくれます。薬草をすり潰す作業自体も癒やしになりました」。北京市在住の張芳(Zhang Fang)さんは炎天下を避けて訪れ、出来上がった安眠効果のある香囊に大満足。「友人にもすすめたい」と笑顔を見せた。
北京・王府井の近くにある協和時光の文化クリエーティブショップでは、香囊体験を始めて3か月。1つ29.9元(約616円)で、頭をすっきりさせる、蚊を防ぐ、安眠を助けるなど3種のブレンドのほか、紫蘇葉や石菖蒲、首烏藤など十数種類の薬草から自由に選べる。
スタッフの雨桐(Yu Tong)さんによると、来店者の選ぶレシピには特徴がある。夏は屋外活動の多い若者が蚊よけを選び、近隣の協和医学院や中央美術学院の学生・教員は集中力を高める香囊を好む。安眠効果のあるブレンドは中高年層に人気だが、香りが穏やかで心地よいため幅広い世代に支持されている。
「本物の薬草やハーブを使った香囊は、既製品とはまったく違いますね!」。北京で働く蘇蜜(Su Mi)さんは一度に4つの香囊を作り、「新しい趣味を見つけた」と話す。
香囊に加え、薬草を練り込んだ「香珠」も人気を集めている。すぐに使える養生グッズを求める人は、完成品の手首用や首飾り用を購入できる。北京同仁堂(Tongrentang)では、肝の調子を整える、心を養う、頭をすっきりさせるといった効能をうたう香珠を販売中だ。手づくりを楽しみたい人は梓霖堂などで、好みの薬草を選び、粉を調合し、丸めて乾燥させ、自分だけのオリジナルを持ち帰ることができる。
「中薬文化は奥深く、薬の組み合わせによっては好ましくない作用を起こす場合もあります。香りによる養生には多くの知恵が詰まっており、専門家の指導のもとで多様なブレンドを楽しんでほしいですね」と張偉さんは語った。(c)CNS/JCM/AFPBB News
※AFPBB Newsの2025年9月19日のニュース(https://www.afpbb.com/articles/-/3598873)より抜粋
興味深い内容です。
日本では、香りを楽しむ伝統芸道である「香道」がありますが、個人的には楽しむことが最重点で、自然療法の位置づけとしては弱い感覚があり、その伝統が今の日本のアロマ文化に影響を与えているように感じます。
でも、中国における香りは、楽しむことよりも、自然療法の位置づけが強い感じを上記の記事から感じました。恐らく、中医学に薬として使われる数々のハーブが香嚢として使われていることもあり、薬っぽい香りが多そうなイメージがあるので、効能メインの志向になりやすいんだろうとも思います。
このような香りの文化に触れることで、その国の香りの捉え方が色濃く反映されていることを理解できると思うので、海外に入ったらその国のメインの香りの伝統文化(日本で香道にあたるもの)に触れていくことを意識していきたいと思います。