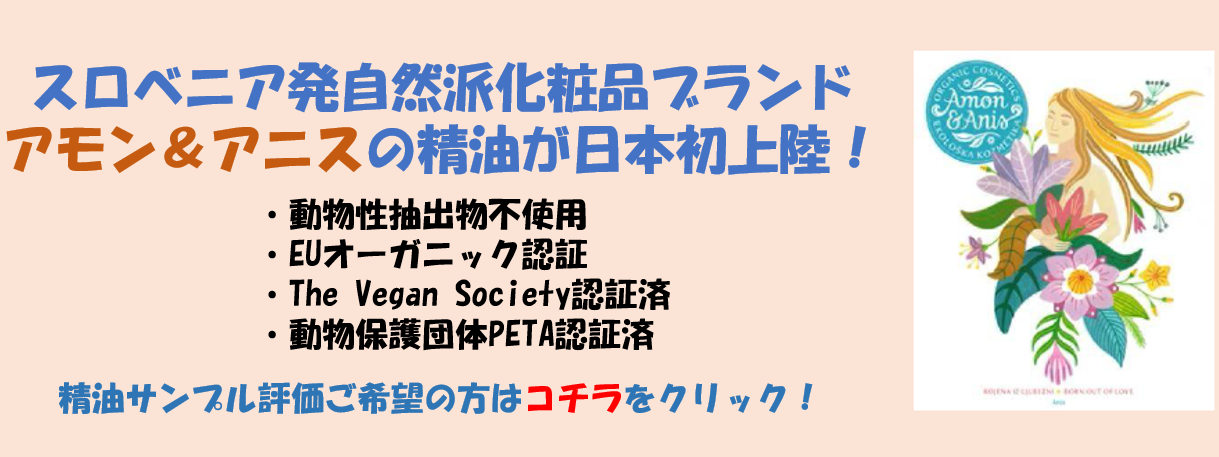先日、兵庫県神戸市と淡路島市へ行った時に感じたことですが、ハーブ・アロマに関わることは、”日本だけではなく、世界全体の歴史の探求に繋がる”ということなんだということが深く理解できました。
【過去の参考記事:神戸布引ハーブ園の初訪問レポート【香りの資料館編】】
【過去の参考記事:「香りの文化」が根付く淡路島にて、お線香の原料など、様々な香りにまつわる展示に出会いました】
そして、今年4月に行った、マレーシア・ペナン島でも、その土地に根づいているハーブ・スパイスを知っていくことで、大航海時代に起こった「スパイス戦争」を切り口とした国同士の関わりの歴史について深く知っていきたいという欲求が刺激されました。
【過去の参考記事:トロピカル・スパイス・ガーデン(マレーシア・ペナン島)の植物たち【スパイステラス編】】
【過去の参考記事:マレーシア・ペナン島で「ナツメグ」に対するイメージが激変。ナツメグの生活への浸透度合いに驚きました。】
学生時代、歴史の授業が本当に苦痛だった自分にとって、世界の歴史のことを深く知りたいと思えている今の自分は、革命的な変化が起こったと認識しています。
そんな自分にとって、先日見つけた記事『死に至る病でさえ克服した「人類と薬」の世界史』は、約5000年前~現代までの「人類と薬の世界史」を広範囲に、且つ、簡潔にまとめた良記事で、今後のハーバルライフの中で参照していきたいと思えたのでご紹介いたします。
死に至る病でさえ克服した「人類と薬」の世界史
たゆまぬ努力と好奇心が不可能を可能にした私たちの健康に欠かせない薬。どうやって生まれ、進化してきたのか。その歴史を、世界の薬学とともにご紹介します(写真:Table-K/PIXTA) 人類を病魔から救う「薬」は、いったいどのようにして誕生したのか?内科医で英語医学専門誌にも多数の発表をしている谷本哲也氏が解説します。
人類は、薬をいつから使い始めたのでしょうか。古代から現代までの人類と薬の関係を、駆け足で振り返ってみましょう。人類最古の薬は約5000年前のもの
古代から中世までは、呪術や魔術、祭儀の中で、薬や麻薬、毒物が混沌とした状態で共存していました。約5300年前の世界最古のミイラは、アルプスの氷河の中から見つかったことからアイスマンの通称で知られています。アイスマンの胃の中からは、毒性もあるシダ植物の成分が見つかっています。なぜこの植物を食べたのか定かではありませんが、胃痛に対する薬として使っていた可能性もあるようです。もしかしたら、人類最古の薬の使用例なのでは、とも言われています。
古代中国では、1~2世紀ごろの後漢代編纂(ごかんだいへんさん)とされた薬物書『神農本草経』が有名です。神農伝説にあやかってまとめられたようです。神農は5000年前の農業と医薬の神とされており、植物が毒なのか薬なのかを自ら試して判別し、最後は薬物中毒を起こして亡くなったと伝えられています。この伝説もまったくの作り話ではなく、似たようなことを古代中国人が行っていたことは間違いないでしょう。
古代文明では、エジプトでも当然薬の記録が見つかっています。ドイツ人エジプト学者のゲオルグ・エーバースが持ち帰り、現在はライプツィヒ図書館に保存されているエーベルス・パピルスは、紀元前1500年ごろ記録されたと考えられ、最も古くかつ重要なエジプト医学文献とされています。700に及ぶ薬の調合や処方が記載され、主に没薬、乳香、ひまし油、アロエやニンニクなど薬草成分が記載されていました。
インドのアーユルヴェーダもこれに劣らず古くからあり、3000~5000年前にさかのぼります。生命を意味するアーユスと知識を意味するヴェーダを合わせた言葉で、医療だけではなく、人生訓や哲学まで含んだインドらしい理論体系です。紀元前12~15世紀ごろ成立した最古の聖典とされるリグ・ヴェーダには、すでに67の薬草を使った治療法が記されています。
3~4世紀ごろに成立した古典医学書『スシュルタ・サンヒター』には、蛇咬傷の解毒剤として、毒草として知られるナス科のヒヨスを用いるとされています。7世紀には、病原を意図的に取り入れるワクチン療法の考え方のめばえもあり、効き目はなかったでしょうが、蛇対策として蛇の毒を飲んでいた僧侶がいたそうです。
日本と同じく多くの神々が登場するギリシア神話では、アスクレピオスが医術を担当していました。輸血を用い死者をも蘇らせる技術が全知全能の神ゼウスの反感を買い、雷に打たれて天に召されますが、へびつかい座として神の一員に加わりました。彼が持っていた蛇が巻き付いた杖は、医療のシンボルマークとして現代でも世界中で使われています。
アスクレピオスの娘のヒュギエイアの杯も薬学のシンボルで、その名は衛生(ハイジーン、Hygiene)、もう1人の娘のパナケイアの名も万能薬(パナセア、Panacea)の英単語として残っています。古代ギリシア医学界のスーパースターは、もちろんのことヒポクラテスで、その誓いは現代の医療倫理でもよく言及されます。ヒポクラテスの処方は、下痢にはソラマメ、風邪には小麦とワインといった、栄養療法的なものが主体でした。
古代ローマ世界では、皇帝ネロの時代に活躍し、薬物誌を遺したディオスコリデスが有名です。薬理学・薬草学の父として中世になるまで長く西洋医学に影響を与えました。ディオスコリデスの薬物誌には、600種もの薬草が記されています。古代ギリシアで活躍した医学者ガレノスも古代医学の祖とされ、さまざまな生薬などを調合したガレノス製剤が後世まで用いられました。
また、11世紀ペルシアで全5巻からなる『医学典範』をまとめ、現代にも通じる新薬の7つの開発規則を記載したアヴィセンナ(イヴン・スィーナー)は、当時のイスラム世界を代表する知識人として知られています。
「近視」を広めたのはグーテンベルク?
ルネサンス期に始まる科学革命は医学分野にも影響を及ぼし始め、解剖学、生理学、外科学、公衆衛生学から薬学に至るまで次第に近代化されていきます。15世紀にドイツのグーテンベルクが活版印刷術を実用化し、宗教改革の波にのって一般大衆が本を読み始めたことで、近視を持つ人も増えました。その結果、16世紀には近視用メガネが産業化され、レンズ制作の技術も向上し、16世紀末のオランダで顕微鏡が発明されます。
その顕微鏡を用い、17世紀にオランダのレーウェンフックが微生物を観察、イギリスのロバート・フックも小部屋という意味の細胞(セル、Cell)という単語を作り出し、近代的な医学や医療の発展に向けて時代が動き出します。
18世紀では、当時、死に至る病として猛威をふるっていた天然痘(てんねんとう)について、イギリス人医学者エドワード・ジェンナーが1796年に行った人体実験が有名です。牛痘にかかった女性のウミを少年に接種し、その2カ月後に、今度は天然痘患者のウミをその少年に接種しました。現代の感覚ではとんでもない荒技です。
しかし、その結果少年は天然痘を発症せず、牛痘での免疫が成立したことを証明しました。天然痘患者のウミを健康な人に予防的に接種する人痘法は、古代から民間療法で行われていましたが、これは天然痘にかかる危険性が高い方法でした。この安全性の高い牛痘の成功から、ワクチンの開発が進み、世界保健機関(WHO)が1980年に天然痘の撲滅宣言を行うまでになります。
古来の民間療法を、近代的な薬として科学的手法を用いて定義し直す試みは、ほかにも18世紀後半からさらに進みました。イギリスの医学者ウィリアム・ウィザリングは、オオバコ科の植物キツネノテブクロの抽出物ジギタリスを心臓病の患者に用い、臨床試験の原型とも言える結果を1785年に出版しています。
スコットランド人医師ジェームズ・リンドも臨床試験の開拓者であり、長期の船旅で発症する壊血病が海軍で問題になっていたことに対し、患者を複数のグループに分け異なる食事療法の効果を比較し、ビタミンCを含むレモンジュースの処方が有効であることを1753年に突き止め発表しました。
1000円札にもなった北里柴三郎の功績
体液のバランスが崩れて病気になるという体液病理学が、アリストテレスの時代から古典的西洋医学の基本で、1000年以上続いていました。しかし、これを覆す細胞病理学という考え方が19世紀後半になってドイツのルドルフ・ウィルヒョウによって唱えられます。病気が細胞の異常によって引き起こされるという近代的な概念で、日本では明治維新の時代と重なります。ドイツには、近代細菌学を開いたロベルト・コッホもおり、その弟子として熊本県出身の北里柴三郎がベルリンへ留学します。
北里は、1890年に「動物におけるジフテリア免疫と破傷風免疫の成立について」と題した論文を発表し、第1回のノーベル生理学・医学賞の候補者に挙げられています(受賞は共同研究者のベーリング単独)。
同じころ、フランスの生化学者・細菌学者のルイ・パスツールが、9歳の少年で狂犬病のワクチンによる発症予防を成功させました。狂犬病ワクチン完成の成果はわずか4カ月後に論文発表され、世界中で名声を獲得し、現在まで続く名門パスツール研究所が1887年に設立される契機となりました。
このように、伝統医学から近代医学への転換を牽引したのは西洋医学が中心となりました。それでも、新たな治療薬と言えるものは、20世紀に入るまで数は限られていました。前述のジギタリスのほかには、マラリアに対するキニン、アメーバ赤痢に対する吐根、解熱剤として用いられたアスピリン、梅毒治療のための水銀などです。
本格的な医薬品開発が進み出したのは、ドイツのパウル・エールリッヒらが1907年に梅毒治療薬サルバルサンの合成に成功し、化学療法、特効薬といった概念を提唱したころからです。
1928年の歴史的発明「抗生物質」
人類にとって、病原菌による感染症は、今では考えられないくらい大きな脅威として20世紀半ばまで猛威を奮っていました。しかし、1928年にイギリスのアレクサンダー・フレミングがペニシリンの効果を偶然発見し、抗生物質が誕生したことで大きな変革が起こりました。そして、実験室の規模を大きく超えて、大量工業生産の技術が開発されたことが、その普及に欠かせませんでした。
オックスフォード大学に在籍していたオーストラリア人のハワード・フローリーとドイツ系イギリス人のエルンスト・チェーンは、1944年まで商業的な大量生産に成功します。これによりペニシリン治療が広く普及し、第2次世界大戦で負傷した何百万人もの兵士らの救命につながりました。
よく知られているように、抗がん剤が最初に開発されたのも、第1次世界大戦で使用されたマスタードガスがきっかけになっています。毒ガスの作用の1つに血液の細胞を減らす効果があることが注目され、1942年から血液がんの患者での臨床研究が開始され、その後実用化されます。以上のように、19世紀までは伝統医学で経験的に見つかった植物由来の薬が主に用いられていました。20世紀半ばからは本格的な化学合成・大量生産の時代に入り、現在にも続く製薬会社が数多く設立され始めました。薬を開発すれば、商業的に大成功をおさめられることがわかり、手を替え品を替えながら、新薬が次々に誕生する現代に至るのです。
※東洋経済ONLINEの2019年6月4日の記事(https://toyokeizai.net/articles/-/280211)より抜粋
こうやって振り返ってみると、歴史というのは『今』があるから成り立つし、『今 』を見つめることで”歴史が浮き上がってくる”から面白いんだなということがわかってきました。
ハーブ・アロマと共に生きるということは、「今を大事に生きる」ということにも繋がるので、そういった要素も歴史への興味が沸き立ってきている原因なのかなとも感じます。