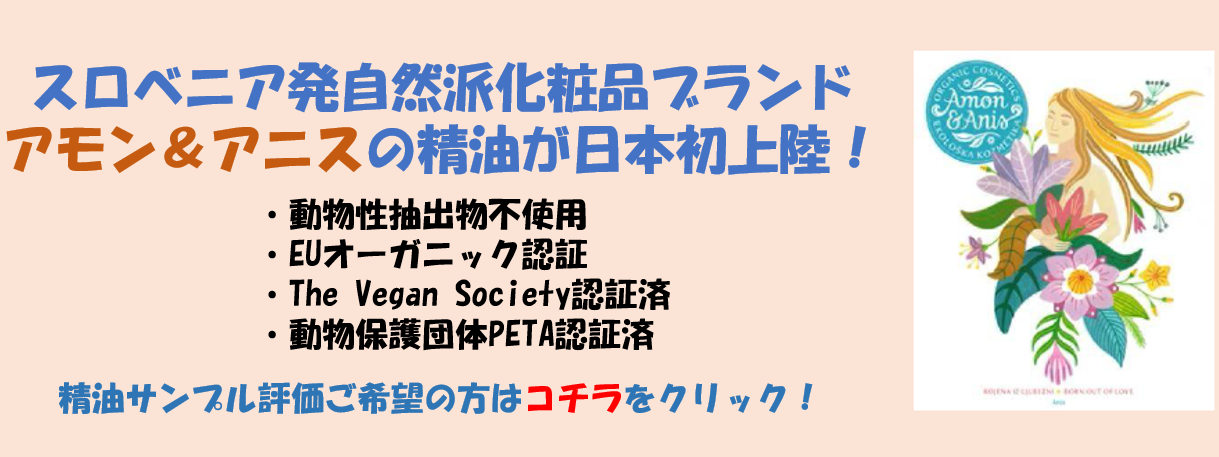今年4月に、北海道(主に富良野)のラベンダー栽培の歴史を取り上げた記事が面白く、本ブログで取り上げました。
【過去の参考記事:北海道におけるラベンダー栽培の歴史背景を取り上げた物語【第一部】】(2020年4月7日)
【過去の参考記事:北海道におけるラベンダー栽培の歴史背景を取り上げた物語【第二部】】(2020年4月8日)
最近は、日本人だけではなく、海外からもたくさんの観光客が、富良野のラベンダーを見に来るようになっていますが、上記の記事を通じて、今の北海道のラベンダー産業の歴史背景の深さに触れることができ、大きく感動しました。
今日は、上記の記事の続きを取り上げたいと思います。
富良野ラベンダー物語3〜北海道のラベンダー栽培の試練

Subbotina Anna/Shutterstock.com
今や北海道を象徴する花として知られるようになったラベンダーは、太平洋戦争直後にニセコ町で最初に栽培されて以降、その香りに魅せられた人々を巻き込んで、波乱万丈の歴史を繰り返し、さまざまなドラマを生んできました。今回は全道で442戸の農家がラベンダー栽培をした隆盛期から、わずか5年で衰退していくまでの物語をお届けします。
ラベンダー畑の隆盛と衰退
北海道のラベンダーの故郷は南仏プロヴァンス地方。高原地帯では今もラベンダーが栽培されている。畝と畝の間隔が広いのは大型機械で刈り取りを行うため。 信じられないような数字が残っている。
1970(昭和45)年──。北海道のラベンダー栽培はその最盛期に達し、エッセンシャルオイル(花精油)の生産量は約5トン(4.95トン)を記録した。この時、栽培農家は全道で442戸、栽培面積は235.45ヘクタールに達していた。
ところが、それから5年後の1975(昭和50)年、栽培農家は92戸、栽培面積も65ヘクタールまで激減してしまう。オイルの生産量史上最大の約5トンを記録してからわずか5年で、全体の約8割にあたる350戸の農家がラベンダー栽培から撤退。170ヘクタール余りのラベンダー畑が一挙に消滅したのだった。
いったいなぜ、こんなことが起きたのか?
まずは、ここに至るまでの経緯を見ておこう。
悲劇の始まり
ラベンダーオイルの生産量が過去最高を記録してから2年後の1972(昭和47)年。曽田香料(本社・東京)は、毎年3月に行われる農家側との価格交渉の席で、今年度のオイルの買い取り価格を昨年並みに据え置きたいと提案してきた。農家側は、これに反発。米価をはじめ諸物価が値上がりしている中、ラベンダーオイルだけ価格据え置きでは、事実上の値下げではないかと抗議した。しかし、曽田香料は方針を撤回せず、価格の据え置きは結局実施された。
その翌年の3月──。さらなる衝撃が待っていた。曽田香料は、ラベンダーオイルの蒸留の停止、そしてオイルの買い取りそのものを停止すると通告してきたのである。道内十数カ所のラベンダー栽培地帯は恐慌状態に陥った。北海道産のラベンダーオイルは、国際基準をはるかに上回る高品質のオイルであり、農家の人々は大きな誇りと自信を持って栽培してきた。そのオイルの蒸留と買い取りが停止される日が来ようなどとは、誰一人夢にも思っていなかったのだ。
ラベンダーは、戦後、苦しい生活を強いられていた北海道の畑作農家の人々に、一筋の希望の灯をともしてくれた作物だった。
他の畑作物は、市場での激しい価格変動や、時には暴落にさらされることがあるが、ラベンダーは曽田香料との契約栽培なので、その心配がない。いくらかでも栽培しておけば、必ず一定の現金収入が得られる。つまり安全安心な作物であるという点が歓迎され、ラベンダーは戦後の北海道にアッという間に栽培が普及していったのだった。
しかし、北海道でのラベンダー栽培を窮地に追い込む、いくつもの要因が急速に浮上していた。
海外産との価格差
馬を使ってのラベンダー畑への石灰散布作業。富良野地方、1950年代。 その1つは、北海道産のラベンダーオイルと海外産のオイルとの価格差が、あまりにも大きくなり過ぎていたことだ。戦時中途絶えていた天然香料の輸入は、1950(昭和25)年に再開された。それ以降、日本には、フランス、英国、スイス、オランダ、ソ連などから年間約60〜70トンのラベンダーオイルが輸入されていたが、その平均価格は、キロ当たり3,175円(1964年)。ところが、北海道産オイルは4,400円。海外産より1キロ1,200円以上高額という結果になっていた。これがやがて、大きく問題視されることになる。
2つ目の要因は、曽田香料の経営体制が刷新され、同社の創業者・曽田政治氏は、すでに経営の第一線から退いていたことだ。政治氏は天然香料の国産化に強い意欲を燃やし、戦前は日本統治下にあった台湾でジャスミンのエッセンシャルオイルを生産。戦後は北海道でラベンダー、八丈島でゼラニウム、瀬戸内海の伯方島と小豆島でベチバー(イネ科の香料植物)など、さまざまな天然香料の蒸留抽出事業を展開してきた。しかし、これらの事業は1960年代の後半になると次第に収益性が悪化。社内では「天然香料は社長の道楽だ」「あれは金食い虫だ」といった陰口が半ば公然と囁かれるようになっていた。
そんな中、政治氏は1971年、満80歳になったのを機に、社長から会長に就任。その翌年、曽田香料には、ある総合商社と大手化学メーカーの資本が入り、会社はもはや政治氏や曽田一族だけのものではなくなった。
非情な決定
北海道のラベンダー畑を視察に訪れた曽田香料の創業者・曽田政治氏と千代夫人。1958年7月。 外部からの役員も加わった曽田香料の新経営陣が、不採算部門の筆頭格として真っ先にやり玉に上げたのが、北海道でのラベンダーオイル事業だった。当時、海外から輸入されるラベンダーオイルのなかで最も安価なのはソ連産だったが、そのソ連産オイルを日本国内で一手に押さえていたのが、じつは曽田香料だった。
一方、年々値上がりを続けてきた北海道産オイルの価格は、キロ当たり7,000円台に達していた。曽田香料の新経営陣は、オイルの買い取り価格の据え置き、さらには蒸留と買い取りそのものの停止を決定する。これは農家に対しては非情な決定だったが、状況からすれば当然の経営判断だった。
新しい香りの登場
香水や化粧品は、かつては花の香りに似せて天然香料だけで作られていた。だが、有機化学が飛躍的に発展した19世紀の末、干し草のような匂いのする「クマリン」、バニラのような甘い香りの「バニリン」といった新しい香気成分が次々に発見され、それがすぐに香水の調合に使われ始める。
ゲラン社の調香師、エメ・ゲランが1889年に発表した『ジッキー』は、バニリンを最初に使用した香水で、その芸術的ともいえる香りで絶賛を博した。香水の歴史は、その後も『シャネルNO.5』『アルページュ』『ミツコ』『夜間飛行』『オー・ソヴァージ(野生の水)』といった名香によって彩られてゆく。これらはいずれも合成香料を巧みに調香に用いた香水だった。合成香料に対しては、当初は「所詮は天然香料の紛い物」という偏見がないわけではなかった。しかし、化学の進歩によって相次いで発見される新しい香気成分は、調香師たちに豊かな調香のアイデアを提供してくれる素材として歓迎されるようになっていく。
合成香料の「バニリン」を初めて調香に用いた傑作香水『ジッキー』(ゲラン社、1889年)。 そもそも天然香料には、避け難い弱点がある。ほとんどが農産物なので、天候に左右され、品質や供給量が安定しない。また栽培される土地の土壌によっても、香りに大きな違いが出る。
例えば、北海道産のラベンダーオイルは、すっきりとした爽やかさのある甘い香りだが、南仏プロヴァンス地方産のオイルはねっとり感がかなり強い。英国産も同じようにねっとり感が強いが、プロヴァンス地方産とは微妙に香りが異なる。一方、オーストラリアのタスマニア島産のオイルは、香りに雑味があり、北海道産のようなさわやかさに欠ける。香料会社の関係者は、ジャスミンオイルについても「モロッコ産とインドネシア産では香りが全然違います」と話す。
天然香料にはこうしたバラツキがあるのに対し、工場で化学的に製造される合成香料は、品質も供給量も安定している。それが香水や化粧品に広く使われるようになっていったのは、当然の成り行きだった。
合成香料の時代
曽田政治氏が情熱を傾けた天然香料事業が次第に斜陽化し、事業として成立しなくなったのは、香水や化粧品の世界が合成香料の時代になっていたからだった。北海道のラベンダーも、そうした時代の波に押し流され、栽培の消滅という運命をたどったのだといえる。
道内最大の栽培地帯
上富良野町江花地区のラベンダー蒸留所、1959年7月。 上富良野町の東中、江花、島津、中富良野町の新田中、富良野市の麓郷。道内最大の栽培地帯だった富良野地方には5カ所に蒸留所があり、ラベンダーのシーズンには、早朝から刈り取られた花穂を運んでくる馬や栽培農家の人たちでにぎわった。7月10日頃からの繁忙期には、東京の曽田香料本社からも社員たちが応援部隊として駆けつけてくることになっていた。
徹夜での蒸留作業
蒸留は1週間以上続く。ラベンダーの花や葉や茎に含まれている香気成分は、時間が経つと揮発してしまうので、ほとんど連日、夜を徹して作業が行われた。1回の蒸留に要する時間は、およそ1時間。いったんオイルの抽出が終わると、高温高圧の蒸気で蒸されて真っ黒になった花穂を蒸留装置から取り出し、新鮮な花穂をぎっしりと隙間なく詰め直す。そしてボイラーに再び点火する。明け方までその繰り返しで、なかなかの重労働だった。
男たちの祭り
しかし、そんな夜にも楽しみはあった。
オイルの滴下を待ちながら四方山話をしていると、どこからともなく焼酎の瓶が出てきて酒盛りになる。そうなるだろうということを見越して、ジンギスカン鍋が用意されていたりもする。それをつつきながら焼酎を酌み交わし、空が白み始める頃まで語り合う。
──ラベンダーの栽培とオイルの生産は、いずれは北海道経済を支える一大産業に発展していくに違いない……。
誰もがそんな壮大な夢を見ていた。男ばかりなので、話が次第に下品な方向へと落ちていくことも多かったが、しかしそれは働く喜び、生きる喜びに満ち溢れた素晴らしい時間だった。
「非常に活気があって、わくわくするような時間でした」
1959(昭和34)年に曽田香料に入社した元社員、大野邦夫は、蒸留所の夜をそう振り返る。
「本当に楽しかったです。まるで、お祭りのようだったんです」
毎年夏がくるたびに、満天の星空の下で開かれる男たちの祭り。オイルの蒸留と買い取りが停止されると、その祭りは開かれなくなった。
雪崩を打つようなラベンダー農家の栽培からの撤退が始まっていた。
栽培の消滅
1976(昭和51)年、曽田香料と農家による契約栽培は完全に打ち切りとなり、北海道でのラベンダー栽培は30年にも満たない短い歴史を終え、幕を閉じた。
蒸留所は次々に閉鎖され、無人の廃屋と化していった。
だが──。
ラベンダーは再生し、復活する。
そして北海道の重要な観光資源となってゆく。
ラベンダーは農作物としての役割を終えた。だが、北海道の重要な観光資源として復活する。 Credit
文/岡崎英生(文筆家・園芸家)
早稲田大学文学部フランス文学科卒業。編集者から漫画の原作者、文筆家へ。1996年より長野県松本市内四賀地区にあるクラインガルテン(滞在型市民農園)に通い、この地域に古くから伝わる有機栽培法を学びながら畑づくりを楽しむ。ラベンダーにも造詣が深く、著書に『芳香の大地 ラベンダーと北海道』(ラベンダークラブ刊)、訳書に『ラベンダーとラバンジン』(クリスティアーヌ・ムニエ著、フレグランスジャーナル社刊)など。※Garden Storyの2020年6月15日の記事(https://gardenstory.jp/stories/41970)より抜粋
第1部~第3部のストーリーが非常に濃密で、本当に面白く、第4部が更新されるのが今から楽しみで仕方ありません。
今後、北海道のラベンダーのことについて見聞を深めていく際は、必ずこの記事は何度も読み返すと思います。
私が北海道で生を受けたのが、1976年ですので、その前年に富良野のラベンダー産業が完全に地に堕ちていたというのは、今の北海道のラベンダー産業の勢いを見ていると、あまり想像ができません。
当時の曽田香料が、北海道のラベンダー産業に絶大な影響力を持っていた事実を知れたことは、貴重な財産になりました。
今後は、よりグローバルな視点で、ラベンダー産業の歴史・構図を理解していきたいと思います。