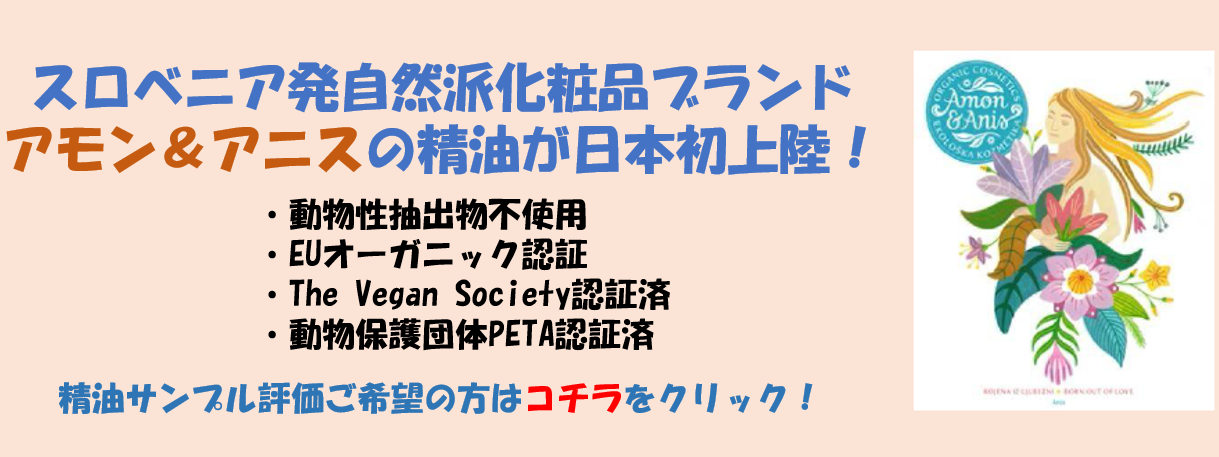プロが作った一流の料理・お菓子を食べるとき、昔は「美味しい!」だけで終わっていたのですが、ハーブ・スパイスに深く関わりを持つようになってからは、美味しいと思ったものを極力自身の生活の中に取り入れようとするスタンスに変化しました。
例えば、以前、イタリア・ボベッティの粒チョコレートを購入した際、ホールのスパイスとチョコレートの組み合わせの美味しさに感動し、その後、自宅で試したことがあります。
この投稿をInstagramで見る
この投稿をInstagramで見る
プロのテクニックのエッセンスを吸収することで、確実に日々の生活が豊かになりますので、プロの料理人・パティシエが作る作品に触れることはとても刺激になります。
今日は、フレンチレストランの料理長が、”ハーブ・スパイス使いの基本”について語っている記事を取り上げたいと思います。
ロブション氏からの学びと、現代ハーブ使いの基本「ジョンティ・アッシュ」進藤佳明さん
コンテンポラリーなひと皿のために基礎を学び、特性を習得する
ジョンティ・アッシュ 進藤佳明さん
今もっとも、ハーブ・スパイスを軽やかに使いこなしているのはフレンチではないだろうか。
だからこそ、その特性を生かしきれるか否かが重要だ。現代のフレンチにおける「基礎」とはどこにあるのか。さまざまな調理法で素材の持ち味を引き立てる
進藤シェフは「ラトリエ ドゥ ジョエル・ロブション」にて5年間、副料理長を務め、ジョンティ アッシュ料理長に就任後一年でミシュランの星を獲得。独自の世界観で作り上げられる料理の数々はハイブリットなコンテンポラリーキュイジーヌでありながら、その調理法はフランス料理の古典的技法に忠実だ。
「以前に比べてハーブやスパイスなど手に入るものは多種多様になりました。乾燥のものだけでなく、フレッシュのものも手に入るようになって、今やその数は無限大と言っていい。それだけに、フレンチに限らず、ハーブを主役にしたり、スパイスの風味をベースにしたソース作りをする料理はこれからも増えていくと思います。ただ、フレンチの伝統的なマリアージュというものは揺るぎのないものがあり、その基本を知っておくことが大切だと思っています」
臭み消しなどの昔ながらの使い方をすると同時に、ハーブやスパイスの風味で主役の食材の味の輪郭を際立だせるのが最近の使い方だと進藤シェフは言う。素材そのものが持つ甘味や旨味を持ち上げるためにはどう使うか。そのためには、香辛料のみならず、使う食材同士のバランスが極めて重要だ。
進藤シェフは、メニューを組み立てるとき、旬の食材を中心に主となる食材を3つ選ぶ。その3つの味を際立たせるためにどんな食材を組み合わせるべきかを考えるそうだ。今回、紹介してくれた一皿目はイワシとトマトが主役。その味を引き立てるのに選ばれたハーブがフヌイユ(フェンネル)だ。注目すべきは、同じハーブを使って違う素材に風味を加えるということ。イワシをマリネする際には乾燥したフヌイユをレモンの皮などとを一緒に漬け込んだ。トスカーナの手摘みで採ったフヌイユの花と葉の部分はパウダー状にしたものをソテーする際ふりかける。白い泡の部分にはフレッシュの茎部分と乾燥フヌイユを合わせて香りのみを移し、フレッシュ感と豊かな香りの両方が楽しめる。フヌイユという小さな素材がこのひと皿に統一感を持たせていることは言うまでもない。
「フレンチはその食材のすべてを料理に使います。同じものでも調理法でさまざまに変化させることができるのが、素材としてのハーブのおもしろさだと思います」
基本を学ぶひと言 フレンチの壱
食材の甘味、旨味を際立たせるためハーブの使い方はバランスが重要
ハーブオイルでマリネしたイワシのソテー エスペレットのガレットに乗せフヌイユを香らせたソースとトマトのジュレを添えて
ハーブが香るイワシにバスクの唐辛子を練り込んだガレットを重ね、ミモレットチーズを飾る。チーズのコクとガレットの辛味、そしてハーブの爽やかさがハーモニーを奏で、フヌイユとペルノー酒の香りをまとったクリアなトマトゼリーとの食感を楽しむ。ロブション氏からの学びと現代のハーブ使いの基本
一方、スパイス使いには原理原則を知っておくことが重要だという。
「スパイスは熱を加えないと香りも味も立ちにくい。どれくらいの時間、どのように火を入れるべきかを知っているのと知らないのではまったく仕上がりが違います。また、ひとつだけを使用すると香りが強すぎることがあるので素材同士の組み合わせも大切。数種のスパイスを合わせるとバランスがとりやすくなります」
進藤シェフのハーブやスパイスへの考え方はロブション氏の下で働いたときに大きく変化したという。
「ロブションさんの作るハーブのサラダに出合ったときは、カルチャーショックを受けました。まだ日本人がハーブなどを使い慣れていない時代に、彼は20種類ほどのハーブを一枚の皿に仕上げていたのですから。使い方にしても、ピューレにする方法や、香りを移すための技法など、今まで使ったことのない調理法を学び、それから僕の料理にハーブやスパイスは必要不可欠になりました」
同じミントでも肉に合うもの、魚に合うものとそれぞれ違うし、フレッシュなままと熱を加えたときでは香りや見た目も変わる。ハーブは一瞬で香りがなくなってしまうので、火の入れ方も重要だ。
「たとえば冷たいピューレに仕上げるときも、ハーブに少し火を入れる。そうすると草木ならではのえぐみなど不要なものが消えて、角がなくなります。先に“無限大”と言ったのは、その種類の多さはもちろん、使い方の多様性にもあるんです」
日本の食材に合うものをイメージしてあえて日本のハーブを使うこともある。アユにはタデを使ったり、セリをセルフィーユの代わりに使うという具合に同じカテゴリーで違う種類のものを使うことも多い。
「ハーブやスパイスを使うことは、もともと日本人のアイデンティティの中にないもの。味わうことや香ることは、頭の中で構築できるものではないので、だからこそ、経験することが大切だと思っています。僕は新しい食材を使うとき“調べる”んです。食べたり火を入れてみたりしてみたうえで分析して使っています。最初はバジルなどシンプルなものから使いたくなると思いますが、経験を重ねると苦味のあるものなども使えるようになる。もちろん個体差もあるので、それなりの目利きも必要です。そういった意味でも試してみることが大切だと思います」
幾度も失敗をして学んできました、と笑う進藤シェフ。どんな素材も手に入る今だからこそ、基本を習得できているか、経験として身についているかでそのひと皿に違いが出る。
基本を学ぶひと言 フレンチの弐
同じ素材を使うときも、フレッシュと火入れをしたときの違いを学ぶべし
フランス産 鴨のフォアグラのプランシャ焼き
スターアニスを香らせた玉蜀黍のピューレとグリオットのソース
新生姜のコンフィを添えて
フォアグラに旬のトウモロコシを合わせたひと皿。スターアニスの香るやわらかな甘味のトウモロコシのソースと、爽やかな酸味にショウガ、コショウのスパイスが利いたグリオットソースのコントラストが、フォアグラの濃厚な旨味を引き立てる。Yoshiaki Shindo
修廣樹にてフレンチの修業を始める。2003年より六本木「ラトリエ ドゥ ジョエル・ロブション」のオープニングスタッフとしてジョエル・ロブション氏のエスプリを受け継ぐ。元麻布の「ボン・ピナール」を経て、「ラトリエ ドゥ ジョエル・ロブション」へ副料理長として復帰。2012年「ジョンティ・アッシュ」料理長に就任。佐倉ひかる(本誌編集室)=取材、文 ナカムラユウコ=撮影
本記事は雑誌料理王国264号の内容を本ウェブサイト用に調整したものです。記載されている内容は264号発刊当時の情報であり、本日時点での状況と異なる可能性があります。掲載されている商品やサービスは現在は販売されていない、あるいは利用できないことがあります。あらかじめご了承ください。
※料理王国の2021年5月24日の記事(https://cuisine-kingdom.com/gentil-h)より抜粋
上記の内容を、すぐに日々の生活に取り入れるというのは障壁が高いと思うのですが、”ハーブ・スパイスの特性”についての本質が語られていると思います。
この内容を見ると、ハーブ・スパイスを使いこなす人が美味しい料理を作った時に、「魔法がかかっている」と感じることがあるのですが、それがとても納得がいきます。
ハーブ・スパイスの特性を知り尽くしているが故に、その料理人の頭の中ではアート作品創作を楽しむことができているのだと思います。
今回の記事は、料理人の感覚を少し理解する上でも良い記事だと感じました。